|
2010,02,24, Wednesday
完成です。
 配線の変更でかなり音が変わりました。高域まで普通に伸びて透明感が出るように。こんなに差が出たのは初めて。どれくらい違うかというと、ピックアップ変更くらいの違い。 ノイズはほぼOKレベル...だけど満足はできないかなぁ...やはりピックアップのノイズが多いのかな?これくらいなら我慢するけど、自分で組んだ楽器とかSadowskyに比べるとうるさい。とりあえす元よりもノイズの量は10分の1以下になりましたけどね。 オレンジドロップは好みでは無いかも。絞っても高域が残る感じがするし、ディップが付いて思い通りにならない...セラコンの方が僕にはあってそうです。殆ど使わないとはいえ。 見た目はパッと見70年代前半ぽいけど、ヘッド見て「アレ?」って感じでしょうか。  このベース、一般的なS8シリアルでは無くて、S88から始まる一桁多いシリアルなんです。最初の二桁、S8の部分と、その後が別プリントって感じで、ちょっとフォントサイズが違う。シリアルとしては78年だろうけど、ポットデートは79年の1週目!ネックデートはあるみたいだけど読めない...というか、塗装する前にサンディングで消された感じ。 ボディも後期に見られるコンターが浅い感じ。ほとんど削ってない(^_^;) 実は塗装も微妙なんです。剥げた部分から白い下地が見えてます。詳しくないのでわかりませんが、黒の下地に白って塗るのかな?もしかしたらリフィニッシュ?と思ったんですが、劣化具合がそれっぽくない。溶け具合と裸部分の境目が。 まったく持って僕の予想ですが、ボディは白ボディとして製作されて放置。78年にネックは製作されシリアルはS8だけプリントされたんじゃないでしょうか?その後しばらく寝かされた後、79年以降に組まれる時にネックデイトが消され、ボディは黒を上から塗ってS8以降のシリアルが入れられたのでは?なんて。ま、大した理由は無かったりするんだろうけど。 70年代後期はこんな微妙な仕様が多いので、明確に何年製って言えないと思いますが、ちまたではシリアルで年代が決められることが多いのだろうから、78年製と呼ぶのが正しいのかな? 思いの他、オリジナルと思われる部分が多かったです。塗装は怪しいとしても、それ以外はオリジナルっぽい部分が多い。といいつつガンガン弄ってしまいましたが...ま、60年代の楽器だったら気分的にこうはいじれないだろうけど。配線、ハンダ、ポット、ジャックなんかもオリジナルがもてはやされるヴィンテージ。消耗品だと思いますけどね...  それにしてもこの音。70年代サウンドを語るベースが巷に溢れる中、なんでこの年代のFenderじゃないと出ないのかね...
| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=318 |
| 音楽::機材 | 12:52 AM | comments (2) | trackback (x) | |
|
2010,02,22, Monday
今回は外装関係。
まずはピックガードを白に変更。黒もいいけど、78年くらいの普通仕様なのでちょっとおもしろくない。 当然ねじ穴の合うピックガードなんて売ってないので自作です。3プライのブランクを買ってきて元のピックガードから型取り。 その型に沿ってドリルで穴を開けていきます。 で、あとはひたすらヤスリがけ。 ほんとはトリマーで作るんですが、今回は過程を楽しむってことでこんな作り方をしてます。ほんとはトリマー使うのが怖いだけなんですが(^_^;)
| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=317 |
| 音楽::機材 | 04:13 PM | comments (0) | trackback (x) | |
|
2010,02,21, Sunday
ディスクリート回路を謳ってるプリアンプ。Bass用のプリアンプにしてて、音はめちゃくちゃ気に入ってるのだが、3番ホット。何かと不便なのでこの際回路を弄ろうと開けてみると、
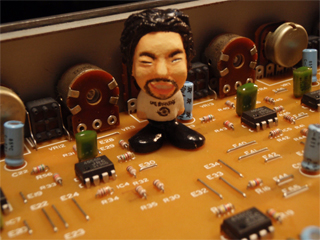 オペアンプが7、8個回路に...えっと、ディスクリート回路って一般的にIC使ってないんじゃなかったっけ? オペアンプはICに入らない?そんなことないだろ(汗) ま、音は気に入ってるんで追求はしませんでしたが...確かにディスクリート回路にしては芸達者で切れ味のあるEQなんで、よくディスクリートで作ったな、とは思っていたので不思議は無いです。 ちなみに使われていたオペアンプはJRC 4558DとJRC 4580。そんな簡単に手に入るものでも無さそう。
| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=322 |
| 音楽::機材 | 08:31 PM | comments (0) | trackback (x) | |
|
2010,02,20, Saturday
配線です。
その前に木部の調整具合を見るためにサウンドチェック。生音は概ね良好。ちょっとビビるのでネック調整しようと思ったらトラスロッドがスカスカ! ゲっ最悪!と一瞬思いましたが、もう少し閉めると効き始めました。ユルユルだっただけ。っつーか弦張った状態で逆反りしてるとは超ラッキー。少しゲージを太くした方がいいかもしれない(贅沢) ラインで鳴らしてみると、かなりノイズが多い...これはアース不良っぽい感じ。音質的には生音がかなりブライトな割には高域はのびてなくて中域が結構出てるイナタイ感じ。Rio Funk? まずコントロールプレート、ブリッジ、ピックアップを外します。どうもピックアップはオリジナルっぽい。ジャックとトーンポットは交換してるみたいだけど、ボリュームポット、配線材もオリジナルみたい。ピックアップはコイルむき出しなので、気をつけないと危うく断線させそうに。 まずノイズ処理としてキャビティ内に銅箔を張ります。ピックアップもコイルに巻くのは断線が怖いのでキャビティに貼って様子見。今回はリード線もシールドしてみました。ベルデンのテフロン系ケーブルに使われているベルドフォイルだっけ?あれでリード線を巻いていきます。もちろんドレン線も一緒。 で上から収縮チューブを被せて。 ピックアップキャビティの銅箔もハンダ付けして、アース線も一緒にキャビティを通します。ちょっと太くなるので通し辛いですが。 今回は配線材がホットにベルデンの8412の芯線、アース線が1512のドレン線を編んだものをできるだけ裸のまま、コンデンサーがオレンジドロップの0.022μF。ジャックはスイッチクラフト。ボリュームポットはCTSの250Ωカスタム、トーンポットは日本製のPush-Pull on-onのスイッチポット、combatだったかな?シャフトサイズがインチとミリで違うんだけど、インチ穴にミリシャフトなので通すのは問題無いです。ぐらつくようなら後で考えますが、まず大丈夫なはず。CTSのスイッチポットって無いよね? なんでスイッチポットなのかというとシリーズスイッチ用です。Sonicなんかでやってるやつ。所有のシングルピックアップのベースには大体増設してます。たまに出力が大きいベースなんかだと歪みっぽくて使えない音になっちゃうんですが。この楽器は出力も大きくなく、特にHighが出そうなので使えそうな予感がしてます。 あ、それからピックアップフェンスは付ける派なので、この部分はアースに落としてます。これは自分的には絶対必要な改造ですね。
| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=316 |
| 音楽::機材 | 04:20 PM | comments (0) | trackback (x) | |
|
2010,02,18, Thursday
Line6のValiaxとPOD X3 Proを使ってProtoolsに一度もアナログ変換することなくレコーディングをしてみようと、世の中のギタリストが卒倒しそうなネタにチャレンジ(笑)
Valiax~Pod X3 Pro間は専用ケーブルで結線するのですが、普通のLANケーブルで代用できるようなのでそれで。ジャック自体はイーサコン。 Pod X3 Pro~ProtoolsはAES/EBUでin/out両方結線。ワードクロックはProtoolsマスターでPod X3 Proを設定。inputをValiaxにしますが、音がおかしい。クロックがロックしてない感じ。試しにinput2をDigital Inに設定しようとしたら、リストにDigital Inが無い...どうやらValiaxをインプットに選んだ場合にはDigital Inが使えないらしい?というか外部クロックにロックしない。 ではPod X3 Proをクロックマスターにした場合は? これは問題無し。正常に音は出ました。が、音質的にはどうかな?アナログとABテストで比べて無いからなんともいえないけど、妙に細い音な気がしたし、なによりシステムクロックをPod X3 Proに任せるわけにはいかないので、この方法は却下。 ということで目論見は塵となりました。 ただ一度アナログにする部分を、Valiax直、Pod X3 Proから選べるので、今度はそのテストをしてみます。外部D/Aって手もあるし。 もしくは192I/OでSRCとかだったらどうなんだろう?とか。 ギター弾く人はこういうベクトルでは攻めないよね(笑)
| http://www.freshersgate.com/kumachon/blog/index.php?e=319 |
| 音楽::機材 | 05:05 PM | comments (0) | trackback (x) | |
